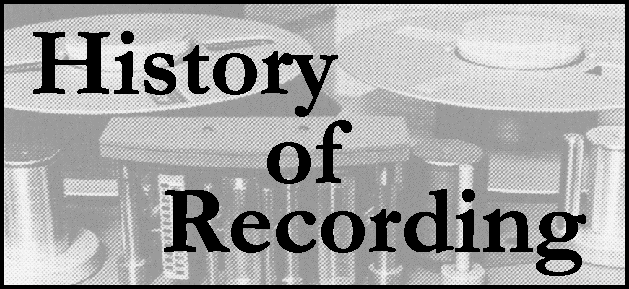
第1回
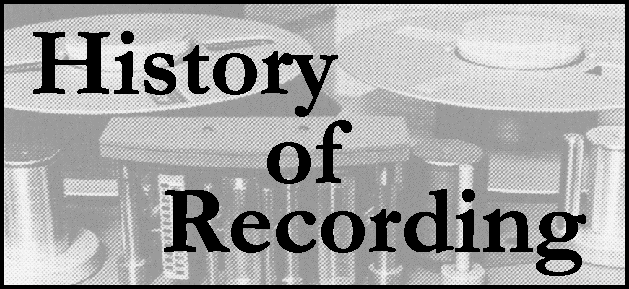
左=Percussion In a Tribute to Benny Goodman 右=Stereo Sound Spectacular
今年はステレオLPが発売されてからちょうど40年目にあたるんですね。正確には1957年11月、オーディオ・フィデリティーというマイナー・レーベルから発売されたのが世界最初の市販ステレオLPですが、これはウェストレックスにテスト盤と称して作らせた盤をそのまま市販してしまったものでした。なんせまだステレオLPの規格が決まる前ですから、ま、抜け駆けってなもんです。RIAAがステレオLPの規格統一をするのは1958年2月になってからです。で、これを受けて各社一斉にステレオLPのシリーズを発売。てことは、もうステレオ録音のストックがちゃんとあったわけです。実はステレオLPよりもステレオ・テープのほうが先行していて、1954年にオーディオ・スフェアが最初のステレオ・ミュージック・テープを発売しています。RCA、EMI、Decca など大手は軒並み1954年にステレオ録音を開始していますから、これがひとつのキッカケにはなったんでしょう。1957年末には大手・中小レーベルあわせて650種類ものステレオ・ミュージック・テープが揃っています。おかげで、ステレオLP発売時には4年分のストックを持って余裕で対応できたというわけです。この当時の大手の有名シリーズは、RCAの "Living Stereo" シリーズ、マーキュリーの "Living Presence" シリーズ、EMI の "Full Dimensional Stereo" シリーズ、London/Deccaの "ffss" シリーズといったところ。ステレオ黄金時代の始まりです。
左=Mantovani / Concert Encores:London/Decca の ffss シリーズの華マントヴァーニ。これはカナダ盤で、75セントで購入
右=Hi-Fi A La Espanola:こちらは再発のマーキュリー Living Presence シリーズの1枚。もちろんエンジニアはいまや伝説のボブ・ファイン
左=Henry Mancini / More Music From Peter Gunn:RCA と言えばマンシーニです。エンジニアは名手アル・シュミット
右=Carmen Dragon / Orientale:カーメン・ドラゴンは、70年代にヒットを飛ばしたキャプテン&テニールのキャプテン(ダリル・ドラゴン)の親父さん。EMI/Capitol のドル箱指揮者でした個人的には、50年代半ばから60年代半ばまで、つまりモノラル時代の最後からステレオ初期までの10年間の録音にとても惹かれます。この時期の録音は、今でもかなわないような優秀録音と、笑っちゃうようなクズ録音が見事に混在しているのです。最近の録音は、平均水準は上がったものの、飛び抜けて優秀な録音や飛び抜けてクズな録音にはなかなか会えなくて、どうもつまらんのです。やっぱ中途半端はいかんですよ。クズにはクズの楽しさがあります。
ところで、初期のポピュラー系ステレオ録音の特徴と言えば、センター定位のない極端な左右の分離です。いくつかの理由がありますが、最大の理由は、ステレオ効果の強調でしょう。当時、ステレオで聴くためにはモノの約2倍の投資が必要なのですから、ステレオ装置を買える人は限られています。そういった人が友人にステレオ効果をデモるのに「誰にでもステレオと分かる録音」が必要だったわけです。
また、制作サイドがステレオを単なる2chモノとして捉えていた、というのもあるでしょう。たとえば、音がやたら左右に動くだけのステレオを「ピンポン・ステレオ」と呼んで馬鹿にしますが、60年代の PIROUETTE というマイナー・レーベルには、その名もズバリ「○○ in Ping Pong Percussion」というシリーズがあります。どれもセンター定位はなく、完全に左右オンリーの2chモノです。ただ、時々リヴァーブだけセンターに来ますが、きっとモノ・リヴァーブが1台しかなかったんでしょう。ジャケにはアーティスト名すらなく、裏ジャケは既発売アルバムのリストだけ。これを見ると約120枚も出ていて、見事な粗製乱造ぶりです。このレーベル、会社名がニュージャージーの Synthetic Plastics Co. となっているところを見ると、プレス・メーカーの副業みたいです。昔はこういう副業レーベルが結構あったようで、このページのトップにある2枚のレコードも、片や Golden Tone、片や Kimberly とレーベル名は違いますが、どちらも Precision Radiation Instruments というロスの会社が出してます。なんか測定器屋みたいな名前だなぁ。
左=Hawaii in Ping Pong Percussion:題材は何であれ、とにかくピンポン・パーカッション
右=The Pinnacle of Percussion:PIROUETTEのサンプラー生まれたばかりのステレオに対してモノラル再生システムの保有者はまだ圧倒的なパーセンテージでしたから、レコード会社としては、当然モノ盤も出さなきゃならん、と言うより、むしろモノ盤がメインだったはずです。特にポピュラー系では、購買層の経済力から言ってもすぐにステレオ装置が買えるはずもありませんから、モノ盤が中心になります。50年代末ではまだステレオ盤の販売パーセンテージはたった7%にすぎなかったそうです。となれば制作サイドでは、ステレオ・テレコをモノ制作の道具と考えても不思議ではありません。モノ盤制作をメインに考えれば、ステレオ・テレコは単に2トラック・テレコです。片方のトラックにはバック、もう片方にはヴォーカルやリーダーの楽器、というのは当たり前でしょう。こうしておけば、後からバランスをいじれますし、ヴォーカルだけにリヴァーブをかけることもできます。で、そのまま出せばステレオ盤に、ミックスすればモノ盤になる、というわけです。
また、機材の制限というのもありそうです。初期のステレオ録音用コンソールは、単にモノラル・ミキサー2台を合体したものでしかなかったのです。つまり、「左用ミキサー」と「右用ミキサー」というわけ。こういう卓でセンター定位を得るためには、ステレオ・ペア・マイクを置くしかありませんが、こうして作ったステレオLPをモノ装置でかけるとセンター定位の音は左右の音よりも6dB上がってしまいます。一部のエンジニアやレーベルでは、これを嫌ってセンター定位を避けたということもあったようです。そのため、一部のスタジオでは3トラック・レコーダーを導入し、L-C-Rをそれぞれ別トラックに分けて録音し、マスタリング時にステレオ/モノそれぞれ別ミックスを作る方法をとっていました。マイルスの名盤「カインド・オブ・ブルー」も3トラック・レコーダーで録られています。そのうち、各チャンネルにL-C-Rというアサイン・スイッチがつくようになりますが、現在のようなPANが装備されるのはかなり後になってからです。
じゃ、実際この時期のコンソールはどんな構成だったのか、カントリーのメッカ、ナッシュビルのRCAスタジオに59年5月に設置されたコンソールに見てみることにしましょう。
まずインプットは12ch。この12chは3チャンネルごとにグループ分けされていて、アサインも3チャンネルまとめておこなうスタイルでした。Ch1〜3のアサインはBuss1に固定。Ch4〜6はBuss1と2のいずれかを選択。Ch7〜9はBuss1/2/3/1+3の4択。Ch10〜12はBuss3に固定。通常、ヴォーカルはセンター・トラック、つまりトラック2にアサインされたので、同じグループの他の2チャンネルはあまり使われることがなく、結局10chコンソールとして使われていたそうです。つまり、一度に立てられるマイクは10本以内、ということですね。これでオケ物も全部やるわけですから、腕が良くなきゃ務まりません。しかもEQはHigh(12kHz)とLow(50Hz)だけ。チャンネル・インサートはないので、コンプの類はトータルにかけるほかありませんでした。
大手RCAの、おそらく当時最新鋭の卓でこうなんですから、他の中小スタジオの卓は推して知るべし、でしょう。まず、放送局のお下がり、というのが相場です。実際に、この卓が入るまではRCAナッシュビルですら1930年代の8chコンソールで録音していたのです。もちろんフェーダーはなく、巨大な回転ツマミで音量をコントロールしていました。アメリカでリニア・フェーダーが使われるようになるのは50年代後半からです。そう言えば、スタジオの卓がフェーダーになっても、録音用ポータブル・ミキサーはその後も長いこと丸VRでした。70年代になっても、よく丸VRのAMPEX AM-10やQuad-EightのLM-6200が使われていたものです。
この時期の卓のヴァリエーションとしては、アサインのかわりに各バス用のVRが各チャンネルに付く、というパターンもあります。今のPAのモニター卓みたいなもんですが、これだと、その気になれば PAN まがいのワザも使えたでしょう。PANは、Pultec から "Panner" という製品が出ていたくらいで、当初はエフェクター扱いでした。60年代初期のワーナーの "Stereo Wokshop" シリーズなんかでは、この Panner を改造したやつを使ってます。

Shorty Rogers / The Fourth Dimension In Sound:
Stereo Workshop シリーズの1枚
ついでに書くと、コンソールの歴史を製品から追って行こうとすると、どうしても壁にぶつかります。なぜなら、少なくともアメリカでは、70年代までは特注コンソールが主流だったからです。たとえば、1977年のビルボード誌のアンケートでは、レコーディング・コンソール・シェアのトップはまだ特注コンソール(14.5%)で、次が僅差でMCI(14.3%)です。この場合の「特注」は、本当の特注の他に、前述の放送局のお下がりを改造しました、というのもかなり含んでいるはずです。こうなっちゃうと、ちょっと実態がつかめなくて困ります。これ以降はメーカー製が主流になってきて、79年にはMCI(16%)、TEAC/TASCAM(11%)、特注(9%)という具合に、特注が減っていきます。TASCAMが健闘しているのは意外かもしれませんが、スタジオの規模を限定しないアンケートですから、4/8/16トラック規模の中小スタジオのほうが数が多く、当然こうなるわけです。「スタジオ」と言うと、ついメジャーな大規模スタジオを連想してしまいがちですが、実際の録音業界は、圧倒的な数の中小スタジオで支えられていることを忘れちゃいけません。ちなみに、お馴染みのSSLが最初の製品SL4000Aを発表するのは1977年、4000Eは79年です。
さて、アサインやPANができるようになったらなったで、気が狂ったような音像移動の嵐を売り物にしたレコードもワンサカ発売されました。もちろん、そういうのを面白がって積極的にハマったアーティストもいたし、そもそも電子音楽の分野ではそういうのが当たり前だったわけですが、実際に出た音像移動もののほとんどは、営業的な理由で制作されたものでしょう。たとえば、Seven Artsが持っていたWarwickレーベルの"Sight and Sound"シリーズにその典型を聴くことができます。このシリーズの裏ジャケの半分は、各曲ごとの楽器の定位と移動の詳細な説明に当てられていて、音楽の説明なんかまるでありません。とにかく音楽より「音」を聴かせようというわけです。

Where There's BURNS There's FIRE:レーベル名、シリーズ名、宣伝文句、サブ・タイトル…どれがタイトルだかよく分からんのもこの種のレコードの特徴
この手のギミック強調型レコードはパーカッション物と相場が決まっていますが、このシリーズもご多分に漏れず、裏ジャケに載っている7枚全部がパーカッション絡みです。表向きは、優秀な装置のデモにはパーカッションの広いDレンジとfレンジが最適、ということになっていますが、実際のところは、かなり安い装置でもパーカッションなら定位が分かりやすい、というのが大きな理由でしょう。とにかくオーディオ・マニアはパーカッションが好きですからね。これは今でもちっとも変わりません。進歩がないなぁ(…って、私も好きなんだけど)。
ここで売り物になっているのは "The Monster" と名付けられた15chスイッチャー。写真を見ると、1チャンネルあたり20個くらいのトグル・スイッチが並んでいるだけの物で、どうも、アサインの組み合わせを20パターンくらい設定しておいてリアルタイムで切り換えられる、というシロモノみたいです。
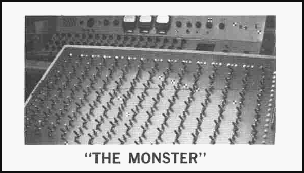
録音自体は、この当時のニューヨーク/東海岸録音としては標準的なもので、これで変なギミックがなきゃ普通に聴けるのにねぇ、といったもんです。しかもこれでテナーがズート・シムズだったりアル・コーンだったりするし、トロンボーンはアービー・グリーンだったりボブ・ブルックマイヤーだったりするんで、ますます悲しい気分になります。このシリーズの他の盤にはビル・エヴァンスやマル・ウォルドロン、ブッカー・リトルなんて名前も見えます。お仕事、お仕事。
このレコードはニューヨークの54丁目にあったベル・サウンドで録られていますが(エンジニア不詳)、妙なことに裏ジャケの機材説明がほぼ同じテリー・スナイダーの "Footlight Percussion with Bongo Beat"(United Artists傘下のUltra Audioから発売されたWall to Wall Stereo シリーズの1枚)は同じニューヨークの Fine Sound (Fine Recording) で録られています。
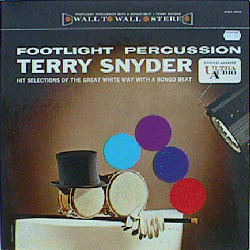
Footlight Percussion with Bongo Beat
Fine はニューヨークと言ってもマンハッタンじゃなくてロング・アイランドのほうにあったスタジオで、こちらのほうが個々の音もリヴァーブ処理もマトモ。こちらもエンジニアのクレジットは無しですが、テリー・スナイダーはイノック・ライトと組んだ Command レーベルの諸作で有名な人で、その Command レーベルの全盛期のエンジニアはマーキュリーのボブ・ファインで、そのマーキュリーのニューヨーク録音をもっぱらやっていたのが Fine Sound、といったあたりで推測はできそうです。ボブ・ファインの音じゃなさそうなので、フレッド・クリスティーか、もしかするとボブの片腕のマスタリング・エンジニア、ジョージ・ピローかもしれません。ジョージは Fine でレコーディング・エンジニアとしても仕事をしているからです。たとえば、ダイナ・ワシントンの有名な "What a Diff'rence A Day Makes(恋は異なもの)" も59年のジョージの仕事です。ちょっとこのへんのエンジニアの音はちゃんと聴き比べていないんで、いずれハッキリさせたいと思ってます。
もちろん、こういうレコードはマイナー・レーベルの専売特許じゃありません。有名なのは、前述のワーナーの "Stereo Workshop" の他に RCA の "Stereo Action"。これはさすがに大手らしく、ギミックに終わらない完成度の高さが売り物です。録りはニューヨークではウェブスター・ホール、シカゴではオーケストラ・ホール、と "Living Stereo" シリーズのパターンです。で、ホールで3トラック・テレコ2台で録ったやつをニューヨークのRCAスタジオでステレオにトラック・ダウンしています。エンジニアはボブ・シンプソン。彼は、RCA ではハリー・ベラフォンテのカーネギー・ホール・コンサートの2枚組、Verve ではオスカー・ピーターソンの "We Get Requests"、インパルスではチャールズ・ミンガスの "Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus" など、名録音の多い人です。音像の移動もやけにスムーズですが、この当時のニューヨークRCAスタジオの卓の写真ではPANがあるようには見えないので、フェーダーでやっているか "Panner" のような気がします。ジャケも豪華で、写真では分かりにくいかもしれませんが、厚紙ジャケに開けられた窓から、レコード袋を兼ねた中ジャケのカラー・パターンが見える、という凝ったもの。このシリーズ、アルバム単位の再発はちょっと望めないし、CDじゃこのジャケの美しさが再現できないのが残念ですが、コンピレーション物ではCDが出ています。
Keith Textor / Sounds Sensational!:Stereo Actionシリーズの1枚一方、こういったギミック満載風の宣伝文句は、売れそうもないアルバムをなんとか売るための方策としても使われていたようです。たとえば、Directional Sound なるレーベルから出た "Jazz & Swinging Percussion" は "Dynamic Directional Stereo" と銘打った効果を売り物にしていますが、このアルバム、実際のところはギミック最小限の普通のジャズ・アルバムです。ギミックはせいぜい、左チャンネルのトランペットのリヴァーブが、曲の途中で意味もなくセンターに出たり、決めのフレーズで一瞬スネアが移動したり、といった小ワザだけで、モノで聴いたらもう普通のアルバムです。アルバム・タイトルも看板に偽りありで、パーカッションなんかちっとも活躍しません。要は、ビル・ベリー・カルテットのアルバムなんですが、まんまじゃ知名度なくて売れないんで、こういう体裁にしたんでしょう。元の録音自体の質は、いかにもこの時代のナローな東海岸録音ですが悪くはありません。妙なことに、マスタリング・エンジニアやスタンパー製作会社、プレス工場までクレジットされているのに、肝心のスタジオとエンジニアのクレジットはありません。これって、もしかして別レーベルから別タイトルで出ていたりするのかな? ちなみにビル・ベリーは、1978年に M&K リアルタイムのダイレクト・カッティング盤で、ホントのオーディオ・マニア向けレコードを作ってまして、これはさすがに良い録音でした。そう言えば M&K って、dbx エンコードされたレコードも作ってたんだよなぁ。ま、その辺の話はいずれ…。
左=Jazz & Swinging Percussion:表にアーティスト名はない
右=For Duke:アーティスト名はあっても、自分の顔写真は使ってもらえないさて、こんな風に思いつくままダラダラと書いていくのがこの連載ですんで、何か「結論」のようなものは期待しないで下さいね。元々、授業のネタ用に(専門学校の講師もやってます、ハイ)簡単な録音史年表を作っていたら、いつの間にかハマっちゃって、メモとレコードが溜まってきただけのことですから。でも、整理していく過程の中でまた新たな発見があったりして、かなり奥は深いのです。もちろん、本格的な調査はとても私なんぞの出る幕じゃありませんが、断片的な知識があちこちでつながっていく面白さを共有できれば、と思ってます。よろしければご贔屓のほどを。
だば、また!
