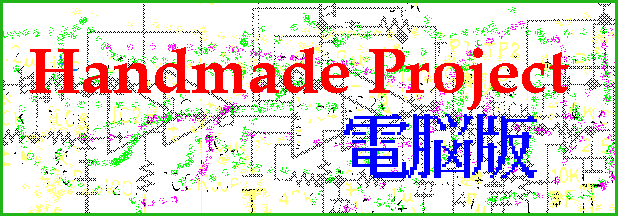
★☆第1回【D−FUZ】の製作☆★
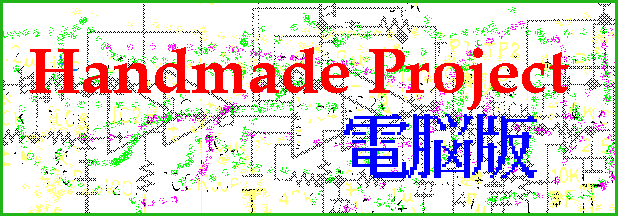
★☆第1回【D−FUZ】の製作☆★
インターネットなるものを初めて見たのが今年の4月。PPGカートレースのスケジュールを調べるためだった。もちろん、これだけ騒がれているメディアだから、他にも『有用な情報』があるのではないかと、心ひそかに期待していた。
数時間ウロウロし、あちこちのサイトを見て回った感想は……書かないでおこう……と思ったけど、やっぱり書くと、「毎日ポストに入ってくるチラシより無意味。電話代の無駄」であった。
あるいは見て回ったサイトが、偶然にもそんなものばっかりだった(NHKのページまで見てしまった!)可能性もあるけれど。後日、友人から「漫然と見ていてはダメ。見たいところにだけ行かなくてはゴミの山を掘るようなもんだよ」と言われた。なるほど……。つまり現状ではゴミが圧倒的に多い、ってことなのだろう。もったいない話だと思う。インターネット総体のあり方に、寝違えるほど首を傾げた。このメディア、もっとマシな使い方があるはず。
私は根っからの「紙」人種だし、意味の無い情報(この辺の言葉遣いにカラまないでね)は資源の無駄だと思っている。ネットだって「資源」のはず。で、インターネットなど、そのまま捨てて、Niftyと草の根ネットの世界に戻ればいいものを、ムラムラと闘争心が湧いてきた。「このメディアで雑誌と同じことをやったらどうだろう。ちゃんと読んでもらって見てもらって、有効に使ってもらえる、そんな情報を流す」……これはチャレンジですね!
私が読者諸氏に提供できる「もっとも意味のあるもの」は、多分製作記事だと思う。ギャラ無しで書かなければならないが、どっちみち私はいつも何か作っているから大した問題ではない。図版とデータを整理し、写真を撮れば(これらの作業は、紙メディアでも製作自体の数倍の手間がかかる)記事などすぐにできてしまう……と考えたのが大間違い。図版は72dpiのディスプレイでも見えるように細工しなければならず、デジカメは露光特性が普通のカメラともビデオカメラとも違う。製版用のドラムスキャナしか知らない私には、卓上スキャナはギョエギョエの性能(デジカメとスキャナは今回のために買ったのだ!)。 紙とは全然違う各種の手法・隠し技には、正直参った。
要するに言い訳を書いているみたいだ。ページ構成の不具合やグラフィックの扱いなどのヘタクソさ加減の言い訳。でもここはひとつ、インターネット4ヶ月目の初心者に免じて、お許しを願いたい。
それから。これは本来なら0号で書くべきことだったが、HTMLはTEXの変形だろう、程度の認識しかなかった私に、基礎を教えてくれて、全体の雛形を作ってくれたMis.野口には大感謝! この1号だって、きっと彼女に「校正」してもらうことになるだろう。早く自立できるようにならねば。
これで前説は終わり。今回、珍品堂と懐古軒は登場しなかった。■D−FUZとは■
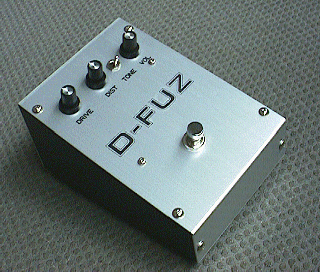
いわゆるファズ。それもIC化される直前の、全ディスクリートで構成された最良期のマシンをベースにしたファズだ。基本的な回路はハニーやエーストーンと同じだから、70年代そのままのサウンドもきれいに出せる。ただ、それだけじゃ面白くないので、波形の歪み具合を、かなり強引に変える細工も施してある。
歪み具合が変われば、普通のファズよりも幅広いサウンド・バリエーションが得られる。セッティングによってはディストーション・マシンのような効果にもなるし、ピッキング時にだけ強烈なファズ音がかかるヘンな音にもなる。3個のツマミの調整次第で、無限に近いニュアンスのサウンドが得られるから「ツマミはいつも全部フルテン」の人には向いていない。いずれにしても古今東西、市販品には無いマシンだ。(やっぱし創刊第1号はファズじゃなくちゃ!)
歪み波形変化のアイディアは小沢からもらった。詳細は以下の項で説明するが、彼が古ファズを修理していたら、とんでもない場所に半固定抵抗が付くプリントパターンを発見した。生産工場での音質アジャスト用の半固定だが、これをいじると歪み波形は大きく変わる。どうせならVRにしてパネルに出してしまえ、というわけで、写真に見える(かな?)DISTのツマミがそれにあたる。
「D−」とは、私の心づもりではディストーションの意味。決してデジタルのDではない! ダイナミックのD、ダーティのDなら、あるいは適切かもしれない。いずれにしても「D−FUZ」と勝手に命名させてもらった。ファズのZがひとつ少ないのは、パネルに張るインレタに、Zの文字が1個しかなかったという非常に現実的な理由からだ。(最近、インレタも高い)
ファズを発生させる回路の基本部分は昔のままだが、多少のハイテク化もなされている。まずエフェクトをオン/オフするスイッチ(フットSW)を電子スイッチにした。クリック対策だ。さらに入力・出力部分にはFETのバッファを設け、入力インピーダンスを高く、出力インピーダンスを低くした。ただ、これには欠点もあって、エフェクトをオフにしても、マシンの電源が入っていないと音は出ない。昔のマシンはエフェクト・オフでは入出力が直結になって、電源とは無関係に信号がスルーしたものだった。
電源は内蔵電池の他に、12〜20V程度の外部電源(直流。いわゆるACアダプタ)も使えるようにしてある。リア・パネルには、そのための入力用DCコネクタを設けた。不要な人はDCコネクタ(と基板上の一部の部品)など付けなくても構わない。ただ、一般のACアダプタは、あまりきれいな直流を出さない。モノによってはハム・ノイズが増えるかもしれない。
逆に、このマシンを電池では駆動せず、写真のようなケースにも入れずに、基板ユニットとして(複合エフェクタなどにして)使うことも可能だ。外部からDCを加えてやればOK。
この外部電源仕様は、今後作る9V動作のエフェクタには必ず付けるつもりでいる。きれいな直流が得られる外部電源ユニットも、エフェクタを何台か作った時点で製作する予定。本誌の企画が順調に進めば、言い換えると「3号雑誌」で終わらなければ、いずれはオリジナルのアナログ複合エフェクタが出来上がることになる。頑張らねば!
■回路の説明■
この項では信号の流れを追いながら、回路各部の働きを説明したい。無論、そんなゲンナリする理屈を知らなくても本機は作れるから、興味のない人は次項までスクロールすることをお薦めしよう。(さすがに「ジャンプ」のホットテキストまでは付けないのだ)
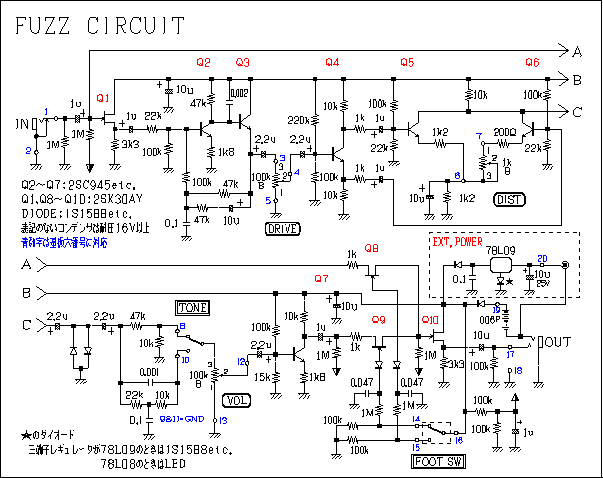

この回路図をダウンロードする人は、図面位置からハギ取るよりも右上のダウンロード用ホットイメージを右クリックして落とす方がベター。緑色のボタンは、画面表示用ファイルよりも少し大きく描いたgifファイル。印刷しても文字が判読できる程度にはしてあるつもり。ピンクは私が元図を描いたcandy6の「C6ファイル」をLHAで圧縮したもの。Windows版candy6を持っている人は、こちらの方が圧倒的に解像度がよろしい。今後ご希望があれば、V5やDXF,BMP,PICTなんかも付けてもいいけど、まあメイルでも下さい。(どうしてこんなに手前勝手なファイル形式がゴマンとあるんだ!怒るよ、ほんとにぃ)
図面では回路定数の表記にアチラ式を採用した。たとえば2.2μは「2μ2」だし、1.8kは「1k8」と書いてた。1μ未満のマイラなどでは「μ」を省略して「0.1」などと表記した。ひとつだけある200Ωは、そのまま「200Ω」。0k2じゃヘンだから。また、この回路図で青の数字は、基板パーツレイアウト図の配線引き出し穴の番号に対応している。
それじゃ信号の流れを追おう。INに入った楽器からの信号はQ1のFETバッファで受ける。2本の1Mがパラになっているので、このマシンの入力インピーダンスは500kΩ。バッファのゲインは1だ(厳密には1以下)。Q1のベースから、バイアス電圧に乗った信号が、図では一番上の線で後段に送られる。「A」で下の段につながる線だ。これはエフェクト・オフ用の信号線。
エフェクト用の信号はQ2でガバガバっと増幅される。ただ、ここでは意図的な歪みの発生はない。Q3はエミッタフォロワで、その出力からQ2に帰還をかけている。軽く周波数特性をいじった帰還だが、これはこの手のファズでは標準的な手法。Q2のコレクタ(=Q3のベース)からプラス電圧ラインに入っている0.002はオマジナイ的な発振防止コンデンサ。本機では一応マイラを使ったが、セラミックでも充分。無論0.0022でもまったく同じに使える。
DRIVEのVRの1番端子がアースに落ちているため、VR入出力の両端を2.2μで切っている。直流ストップ用のカップリング・コンデンサだ。このVRは後段に送る信号のレベル調節用。いわばアンプでいうヴォリュームだ。常識的には、ここにはAカーブを使うべきなのだが、Bカーブでも支障はない。本機がエフェクタだからでもあるけれど、VRを受けるインピーダンスがVRの100kΩより小さいからでもある。Q4のベースからアースに100k、電源に220kが入っている。アースも電源ラインも交流的には同じ「インピーダンスが0のライン」で、簡単に言えば電源ラインも「アース」と同じと見なせるため、Q4のベースの対信号入力インピーダンスは100kと220kの並列合成値、約69kΩになる。これはVRの100kΩより小さい。となると、ここにBカーブを使っても、動作はAカーブに近付いてくる。
余談だが、AカーブのVRを、そのままのAカーブ特性で使いたい場合には、VRの抵抗値の、少なくとも2倍、この例なら200kΩ程度以上のインピーダンスで受けなければならない。エフェクタにBカーブが多いのは、こういった裏技風の使い方をしているからだ。実利的にも、Bカーブの製品の方が入手しやすいし、メーカーはAカーブをストックしておく必要がなくなる。(逆に、AカーブのVRをBカーブに化けさせるのは事実上不可能)
Q4は「C-E分割」という回路。ゲインは1で増幅はしないものの、コレクタ側とエミッタ側とから逆位相の信号が得られる。逆位相というのは、波形の上下(プラス/マイナス)が入れ替わった信号のことだ。この回路では、ベースに入った信号と同じものがエミッタ側から出てくる。コレクタ側からは波形の上下がひっくり返った信号が出てくる。ハニーやエーストーンの古いファズには、まずこの回路が使われている。でも、どうしてこんな面倒なことをするのか?
Q5,Q6で「差動増幅」というのをやっているからだ。今後、この製作ページでヤになるほど使うオペアンプというICも、入力部分は「差動増幅」回路だ。これは逆位相の2種類の入力信号を用いて、増幅率を大きく稼ぐものでもあるし、使い方によっては、信号に混ざってくるノイズも低減できる。いろいろと御利益のある回路ではあるが、ここではちょっと邪悪な意図で使っている、と思われる。
ハニー、エーストーンでは、Q5,Q6のエミッタは直接つながっている。そして、そこからアースに1.8kの抵抗と10μのコンデンサがアースに落ちている。つまりQ5.Q6は完全にシンメトリィ。もしもQ5とQ6が「まったく同じ特性のトランジスタ」であれば、ここの歪みは極端に少なく、増幅率をガバガバと稼げる回路になる。ところがトランジスタには、意図的に選択しない限り、必ずバラツキがある。バラついた分だけ歪みになって出てくる。この偶然のバラツキを利用して、音を微妙に歪ませようというのがメーカーの意図だったのだろう。
今回私(本当は小沢)は、さらに邪悪なことを考えた。もっとバラつかせて、それをコントロールしようというわけだ。Q5,Q6のエミッタを直結せず、エミッタ側の抵抗をアンバランスにしてしまう。当然、差動増幅は崩れ、信号はより歪むことになる。DISTのVRで差動をどれだけ狂わせるかコントロールする。VRを絞りきって1kΩになったときにだけ、Q5とQ6のエミッタ抵抗は同じ1.2kΩになり、正しい差動増幅が行われる。このときの音が、お馴染みの70年代ファズ。まあ厳密に言えば、両方のエミッタからの各1.2kΩの部分には電流帰還がかかっておらず、全体のゲインや音色にも影響を与えるはずなんだけど、それは理論上のこと。本機は測定器でもハイファイ・オーディオでもないから、まず無視して構わない。
無視できないのはDISTのVRを変化させると、歪みだけでなく音量まで変わってしまうこと。差動増幅のバランスを崩しているのだから当然ではあるけれど、結果としてDISTを動かしたらVOLも動かさなければならない。コントロールとしてはちょっと使いにくい。本機の唯一の弱点だ。
差動増幅の次にはファズの典型パターンである「ダイオード・クリッパ」がくる。図では下段の一番左側、ダイオードが2本、逆向きに付いている部分だ。ダイオードの特性として、シリコン・ダイオードでは約0.7V、ゲルマニューム・ダイオードでは約0.3V以上の電圧がかからないと電気が流れない。これを利用して、本機では、差動増幅回路で増幅した波形の、プラス/マイナスとも約0.7V以上の部分をチョン切っている。クリップしているわけだ。これは波形をスパッと切ってしまうから、極端な歪みが発生する。ファズの常套手段といえる。
またまた余談だが、実を言えばファズには2種類ある。本機のようにダイオードで波形を切って歪みを作るタイプと、ファズフェイスのようにひたすらゲインを稼ぎまくって波形を大きくし、勝手に歪むのを期待するタイプと。音はもちろん違う。どっちが優れているとは言えない。ただ、ごくアバウトな傾向として、ダイオード・クリッパ・タイプの方が扱いやすい、とはいえるが、例外ももちろんある。
波形のアタマとシッポが0.7Vで切られた信号はトーン・セレクタ回路に入る。TONEのSWの左側の上下2階建てみたいなところだ。上の47kと10kはただのアッテネータ(減衰器)で、信号を約1/6にしている。これは、下側のフィルタでは信号が減衰するからで、聴覚上の音量を合わせるための手段。下側のフィルタは、基本的にはハイカット特性。刺激的なサウンドを丸くする働きがある。
TONEのSWは、そのどちらかの音を選択する。SWから直接VOLのヴォリュームにつながっていて、これはもちろんマシンの最終的な出力音量を決めるもの。とはいえ本機ではDISTでも音量が変わるから、VOLを常にフルテンにしておくわけにはいかない。VOLは本当の意味での出力音量調節になる。なお、TONEのSW直後にTONEというヴォリュームを付けることも可能だ。設計・試作段階では私もそのつもりだった。ところがDISTを付けてしまうと、そのサウンド変化の方が効果が大きく、敢えてTONEのVRを付けなくても、SWだけで充分なバリエーションを楽しめることがわかった。さらにケースにTS-11を使う以上、もうひとつVRを付けるスペースがない(無理すりゃ付くけど)。で、TONEのVRはこの際省略。どうしても付けたい人は、100kBのVRと0.002のコンデンサがあれば、この基板のままで付けられる。各種文献を当たってみよう。すごく簡単だから。
VOLの100kBも本来ならAカーブであるべきところ。だって音量調節だから。しかしDRIVEのところで説明したのと同じ理由で、ここはBカーブでちょうどいい。Q7のベースには100kと15kがつながっている。ここの入力インピーダンスは、何と13kΩしかない。BカーブのVRでも、充分以上にAカーブ特性になる。
Q7は最終増幅段。ここでゲインを稼いで、昔のマシンなら出力ジャックに直行となる。でも本機は電子SW仕様。少し複雑な回路を通る。
Q8とQ9はスイッチング用のFETだ。Q8がオンになると原音が、Q9がオンでエフェクト音が選ばれる。Q8とQ9はフットSWからの電圧でドライブされる。ダイオードと1MΩを経てプラスの電圧がゲートにかかると、そのFETはオンになる。電圧がかかっていないときには、それぞれ100kでアースにつながれて0Vになり、スイッチはオフ状態になる。1MΩと0.047はスイッチングにごくわずかな時間をかけさせるためのパーツ。時間をかけることでクリックの発生を防いでいる。ま、電子スイッチといっても、ただこれだけのことなんですが。
信号は、最後にQ10のバッファを通って出力ジャックに行く。このバッファもゲインは1。増幅はしていない。ところで、各FETの周りに半分白と黒の三角印がある。これはバイアス電圧を表わしている。この電圧は図面右下の2本の100kと1μのコンデンサで作られ、電源電圧(電池なら9V)の約半分の電圧になる。バイアスによってQ1とQ10ではFETの動作点は最適な電圧に固定され、Q8とQ9ではスイッチングが完全に行われるようになる。バイアス電圧はFETバッファと電子スイッチを採用したために必要になった電圧だから、昔のファズには無い。
電源について説明しておこう。本機のパワーは出力ジャックにプラグが差さるとオンになる。006P電池のマイナス側がアースとつながって電池が生きるからだ。電池のプラス側にはダイオードが入っている。これにはふたつの役割がある。まず電池の逆接防止。ダイオードを入れておけば、間違って逆接しても電流は流れないから回路本体に影響はない。ただし、ダイオードを通すと電圧は約0.7V落ちてしまう。9Vの新品電池を使っても、本機は約8.3Vで動くことになる。さらにただし、本機の減電圧特性はかなり優秀というか、いい加減というか、7V程度でも立派にファズるから、まったく心配はない。
ダイオードのもうひとつの働きは、外部電源がつながれたときに、自動的に電池からの電圧を遮断し、外部からの電圧で本機を動かすこと。枠で囲われた部分が外部電源に対応する回路だ。(外部電源を「絶対に使わない」人は、この部分のパーツは不要)
外部電源入力端子には、いわゆるDCコネクタが最適。私は芯棒が2.1ミリの製品を使い、芯をプラスにした。そしてマイナス側を電池の黒い線といっしょに出力ジャックの(プラグが差さると)アースにつながる端子につないだ。これで電源のオン/オフは、電池も外部電源も同じ扱いになる。さて、DCジャックのプラス側には12〜20V程度の直流を加える。すると78L09という三端子レギュレータが9Vの電圧を出す……のだが、9Vだと少々都合が悪いので、三端子のコモン・ピン(中央の足)にダイオードを入れ、出力電圧を約0.7V上げて、約9.7V出るようにしてある。この電圧を、電池と同じようにダイオードを通して回路の電源ラインにつなぐ。回路には約9.0Vが加わる計算だ。
もしも電池と外部電源とを同時に加えた場合、電池は8.3V、外部電源は9.0Vになる。このとき、外部電源からの電圧の方が高いので、自動的に外部電源からのパワーが回路に加わる。電池はまったく消耗しない。いわば自動切り替えになるわけ。「外部電源からの電気が、電池に流れ込まないか?」なんて思わないこと。ダイオードが入っているから大丈夫。
電源のカラクリはおわかりいただけただろうか。この方法は、別に私の発明でも何でもない。2電源、3電源仕様の製品は大体こうなっている。ここでひとつ問題がある。三端子レギュレータの78L09が、ときとして入手できないことがあるのだ。作っているメーカーが少ないせいもある。そんな場合は78L08でもOK。ただ、コモン端子につなぐダイオードを、普通のシリコン・ダイオード(1S1588等)ではなく一番安いLEDにすればいい。LEDは約2Vのゲタを三端子にはかせてくれるから、三端子の出力は約10Vになる。78L09+ダイオードにくらべて、わずかに0.3Vしか高くない。まったく同じに扱える。しかも、ここにつないだLEDはちゃんと光る。だから、その気の人は、わざと78L08+LEDにしてLEDをパネルに出せば、「外部電源インディケータ」になる。これも結構美しい。
ずいぶん長くなりました。これで「回路の説明」は一応終わり。文字ばっかりで飽きたでしょう。予算があれば、適当な場所にイラストなんか入れられるんだけどね。まだまだ「文字」が続きそうなので、創刊号のオマケとして、私の試作室の写真でも載せておこう。撮っている測定器や電源は全部自作かキットです。
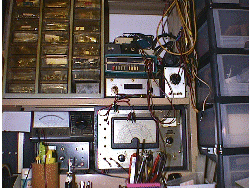
■パーツのこと■
★基板上のパーツ
エフェクタといわず、すべての回路は「結果オーライ」といえる。自分が満足できる結果が得られて安定に動作すれば、理屈などどうでもいいのだ。エフェクタに限っていえば、そもそも音をヘンにする機械だから、ちょっと違ったパーツを使ってサウンドが変わったとしても、それは「味のうち」と考えるべきだろう。でもまあ、初心者の人は、最初は一応指定通りに作ってみよう。改造はいつでもできる。
それなら「指定通り」のパーツしか使えないか、というとそうでもない。変更してもサウンドに影響しないか、してもごくわずかな代用品パーツについて以下に書こう。
まずトランジスタ。指定では2SC945etc.としてある。安いからでもあり、私が最初に作った試作機に使ったからでもあるだけで、特にコレという理由の無い指定だ。要は小型のNPNタイプならほぼ何でも使える。型番のアタマに「2SC」が付いて、安ければそれでいい。たとえば、現在一番出回っていて安い2SC1815は当然使える。数年前にゴソッと出回った2SC1000も、もちろんOK。この他、2SC458,2SC733等、手持ちにあれば活用しよう。いろんな型番の石を混ぜて使っても構わない。ただしQ5とQ6は同じ型番にしたい(基板上のどれがQ5,Q6なのかわからない人は冒険しないように)。
FETは価格の点から2SK30Aを指定した。私の試作機では「Y」というランクの2SK30AYを使ったが、他のランクのGRやOでも支障はない。先日秋葉原に行ったら、すでに2SK30Aは古いらしく、2SK118(これにはランクは無い)がもっと安く出ていた。全体が小型になってスマートな石だ。118でも試作したが、まったく問題は無し。消費電流が減っただけで音は変わらなかった。他の型番のFETも使えると思うが、まずほとんど高価なので、ここは30Aか118にしておこう。アタマに「2SJ」が付くタイプは使えない。
ダイオードはシリコン・タイプの小信号用なら何でも使える。1S1588がもっともポピュラーなので指定した。いわゆる「同等品」でもいいし、他の型番の1S953等でもまったく同じだ。
前項でも書いたように三端子レギュレータの78L09は78L08でも代用可。その場合は中央の足からアースに落とすダイオードをLEDに換えればいい。基板にはそのための穴もあけておいた。LEDのサイズ・色は不問。まあ一番安い赤色がいいだろう。
抵抗とコンデンサも、これまたいい加減で、そもそもコンデンサは誤差が10%以上許されているし、抵抗だって最大で5%の誤差がある。だからたとえば、本機に使われている100kΩを全部91kΩや110kΩにしたところで大勢に影響はない。値を絶対に変えてはマズい抵抗は、1本だけある200Ωくらいだ。あとは±10%程度の範囲でなら自由に変更していい。なお抵抗には1/4W型、5%のカーボン抵抗を使った。高価な金属皮膜抵抗や高精度抵抗は無駄。若くて目の良い諸君は、さらに小型の1/8W型を採用してもよろしい。私は老眼で、細かいものが見えにくくなっている。墓場は近い。
コンデンサはもっとラフ。電解コンデンサの1μは0.047μ〜10μ程度のものに置き換えても構わない。2.2μは1μ〜10μの範囲で変えてもいい。10μは22μでも33μでもよろしい。……なんて書くと「回路図上の定数指定は意味無いじゃない」と思うかもしれない。そう、その通り。回路図の定数は、私が「こんなもんだろう」と経験から出した値でしかない。ま、少しは計算もしたけどね。ひとつだけ守ってほしいのは「耐圧」。電解コンデンサの耐圧はすべて16V以上にしたい。外部電源からの入口に付いている10μは、少なくとも25Vの耐圧にすべし。35Vでも50Vでもいいけれど、それだけサイズは大きくなるし高い。
電解以外のコンデンサは、0.01μのセラミック以外、全部マイラを使った。でも、これも実はどーでもよく、全部セラミックや積層セラミックでも支障はないし、その方が安い。0.002μというのがあるが、これはもちろん0.0022μでも同じ。0.047μは0.033μ〜0.1μでも構わない。
★基板外のパーツ
ヴォリュームは、まずは指定通りにする方が安全だろう。100kBの代わりに50kBでもいいとも言えるけど……。1kBは必ずその通りにしてほしい。10kなどを使ってはいけない。敢えて変えるとすれば1kBの代わりに500ΩBならいける。そのときには200Ωの抵抗を680Ωに変更すること。200Ωのままだと昔風のファズ音が出なくなる。また500ΩBにすると歪み方をコントロールする範囲が狭くなり、人によってはその方が使いやすいかもしれない。研究して下さい。
ツマミはなるべく小さい径のものを選ぼう。最大でも直径20ミリまで。15ミリなら一番使いやすい。
TONEのスイッチには普通の3pトグルを使う。一番小さいタイプはいくらか安いものの、強度の面で心配。取付穴が6ミリ位の製品が適当だ。
フットスイッチは選択の余地はない。踏んづけても壊れない国産品はミヤマのDS-136のみ。同じ顔をしていて2pのDS-135もあるので注意。136が無ければ6pのDS-008も使える。 ジャックは、入力(IN)用には後で結線図で描く「モノラルSW付」を使う。端子がたくさんある「ステレオSW付」でも使えるけれど、初心者には混乱の元だろう。出力(OUT)用には、できれば「ステレオSW無し」がシンプルでよろしい、のだが、これが品薄。入手しやすい「ステレオSW付」のスイッチ部分を無視して使うしかない。値段もそう変わらないし。
外部電源入力端子には最近出回り始めた、丸穴で取り付けられるDCジャックを選んだ。以前は、DCプラグといえばメーカーの量産用しかなく、取り付けるのにトンネル型の穴をケースにあけ、瞬間接着剤でくっつける曲芸を要したものだった。日本のパーツメーカーは偉いね。必要なものはすぐに作ってくれる。私は芯棒が2.1ミリのタイプにした。各種あるようなのでご自由にどうぞ。ただし、自分のシステムにいろんな規格のジャックが混ざるのは不便の元、混乱の種なので、後々のことまで考えて、安定して入手できそうな製品にしよう。(どのタイプが安定供給されるか、そりゃギャンブルだが) もっとも、「オレは電池しか使わん」の人は、DCプラグは付けなくても構わない。基板上の78L09と、その周辺の2本のダイオード、10μ25Vと0.1μも不要。このマシンの消費電流は、電池動作なら5mA以下なので、電池だけでも充分に長持ちする。
その電池だが、普通にはケース内に入れて、ガタつかないようにスポンジ等のクッションで固定するのが常套手段。本機はOUTジャックにプラグを差すとパワー・オンだから、プラグを差しっぱなしにでもしないかぎり、電池は相当もつはず。ゼロハンのバイクがガソリンスタンドに行くペースよりも長持ちする。しかし、いったん電池交換となると、タカチのTS-11ケースでは8本ものビスをはずさねばならない。これ、結構手間です。そこで、今回はタカチの「埋込電池ボックス LG-006P」を試してみた。底板に穴をあけて電池ボックスをガポッとはめ込む。こうしておけばビスをはずさずに底板側から電池交換できる……のだが、底板に37.5ミリ×71ミリの巨大な長方形を、ピッタンコにあけなければならない。ハンドニブラとヤスリで格闘したが、これも結構手間がかかるし神経がすり減る。電池交換の手間と、底板穴あけの手間と、どちらに耐えるか、それは諸君次第だ。
付け加えると、電池ボックスを使わなければ、本機の工作はパネル側だけで済む。底板は単なる「フタ」になって、改造やメンテもしやすい。また後述するが、ボックス付属の電池スナップの線が短いため、基板への線を継ぎ足さねばならない。……と、あたかも電池ボックスは使うな、みたいな書き方だけど、そうじゃない。ちゃんとデメリットも書いておこうと思って。電池ボックスを使った場合の写真を以下に載せておこう。
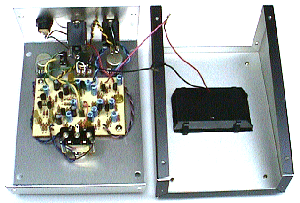
←電池ボックスは底板中央付近にはめ込むケースは安くて入手容易なTS-11。今回のツマミ数、基板サイズには最適なケースだ。もちろん各人の趣味で、どんなケースを使っても構わない。ケース屋に行って、じっくりと選んでもらいたい。私はいつもラジオセンターの秋葉原デパート側にある山崎電機商会で選んでいる。秋葉原以外では渋谷の藤商にもタカチのケースはある(ここも面白い店です)。
忘れやすいパーツに、基板取付用のスペーサとビス・ナットがある。スペーサは長さ3〜5ミリ、ビス・ナットは3φで、ビス長は10〜12ミリ。これらを各2個買う。
その他必要なものは配線材。ビニール被覆線が数色、細目のシールド線、そして熱収縮チューブ(シールド線が入る太さ)もほぼ必需品だ。
■プリント基板■
たかがファズなのに、電子スイッチ化したり外部電源対応にしたため、基板はかなり大きくなった。サイズは58.5ミリ×81ミリ。ただしこれは大体の寸法。もとがインチだから2.3インチ×3.2インチが正確なところ。以下にまずプリント・パターンを出す。今回はディスクリートだから、寸法はあまりシビアでなくても平気だ。
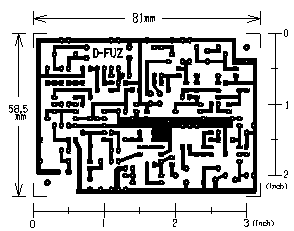
gif形式プリントパターン印刷用
ダウンロードは回路図と同じ。この画面からしてもいいけれど、できれば右側のホットイメージを右クリックして落とした方がベター。少し大きめのgifファイルが入っているから、寸法合わせや印刷に便利だろう。LHAで圧縮したCANDY6形式の元図も用意した。
各種ソフトや拡大・縮小コピーなどを駆使して、なるべく指定寸法に近いハードコピーを作ろう。その後、生基板に穴位置をポンチで打ち、遮光ペンで手描きするのが一番安全。ピン間にパターンを通す趣味はないから手描きでも簡単にできるはず。間違ってもパターンをOHPフィルムにプリントし、いきなり感光基板に焼かない方がいい。ヤバいのは実験済みだ。といって、フィルムをレタッチする手間を考えたら、やはり手描きの方が早いだろう。(グラフィックについて、こーゆー実験をやってたから、今回はツラかった!)
基板穴は0.9〜1ミリ。右上と左下の独立した丸はビス穴で3.2ミリ。基板の材質は紙エポかベークで充分。ガラエポでドリルの刃を減らす必要は全然ない。
パーツレイアウトは以下の通り。本当は、下にパターンが薄く見えるようにして、穴位置に合わせてパーツを描きたかったのだけれど、やってみたらグシャグシャになって、何も見えなくなってしまった。適当なソフトを持っていないのか、腕が悪いのか……今後の課題です。あまり美しい図ではないので、ひとえに皆様の努力に期待するしかない。
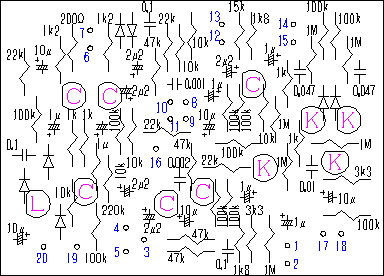

gif形式パーツレイアウト印刷用
見にくいけど見えるでしょ? Cはトランジスタ、KはFET、Lは78L09。FETはどっち向きに付けてもいい。トランジスタと三端子レギュレータは、必ずフラットな面を図面と同じ方向にする。電解コンデンサの極性にも注意。ダイオードは本体に帯のある方が、図面では三角の頂点に付いた棒の方向になる。あまり自信のない人は、パーツをハンダづけする前に、配線の引き出し穴の番号を、細い油性ペンで書き込んでおくと楽だろう。
ここで初心者用、カラーコードの読み方など……。ベタっと並べます。
抵抗カラーコードの読み方
200Ω=赤黒茶、1k=茶黒赤、1.2k=茶赤赤、1.8k=茶灰赤、
3.3k=橙橙赤、10k=茶黒橙、15k=茶緑橙、22k=赤赤橙、
47k=黄紫橙、100k=茶黒黄、220k=赤赤黄、1M=茶黒緑
(金色の線は精度5%を表わす。どうでもいいので無視する)
コンデンサの表記
0.001=102、0.002=202、0.0022=222、0.01=103、0.047=473、
0.1=104 と表記されていることもあります。
■配線■
★ケース加工など
基板ができたら、測定器があって回路図が読める人は、各増幅段が働いているかどうか発振器とオシロで調べた方が安全。それ以外の人は、パーツレイアウト図と基板を見比べて、完全に合っているのを確認。全部組み上げてしまってから「動かないッ!!」となると、もう一度バラして最初から組み直しになるので、ここは慎重に。
ケース加工は下の写真を参考に、各自のセンスでよろしく。注意する点は、ヴォリュームと基板、基板とフットスイッチがぶつからないように、適度の間隔をあけて配置すること。適度というのは3〜5ミリ程度だ。リアパネルのジャック類がヴォリュームに当たらないように、少し下目に付けること。TS-11を使う場合、底板をビス留めするためのエッジが、パネルの左右に10ミリずつあって、その部分のパネル面は使えない。(死んだバアちゃんが言ってた「裁縫するときは、百度当たって一度切れ」。これ正しいね)
TS-11には、パネル・底板ともにビニールが張ってあり、その上に油性ペンで直接線を引いて位置決めができる。底板に電池ボックスを付ける人は、とりあえずパネル側だけ完成させて、基板やフットスイッチに当たらない位置を見つけてから底板の工作に取りかかった方が賢明。
ツマミの文字はインレタなどで。自作機だからといってパネルに文字を入れておかないと、3ヶ月後には絶対に忘れているものだ。外見を気にしなければ油性ペンで書き込んでも構わないから、必ず文字入れはしよう。
★結線
配線数はあまり多くない。図と参考写真で簡単にいけるだろう。
配線の基本は、なるべくケースに這わせて配線を引き回すこと。基板の上を横切る配線が少なくなって美しいだけではなく、ケースはアースだからノイズにも強くなる。
基板はスペーサを使ってケースから浮かせて固定する。固定してから基板パターン面にハンダ付けするのは絶対に不可能だから、まず基板を所定の場所に置いてみて、各配線の長さを少し長めに計り、全部の線を基板にハンダ付けしてから基板を固定するしかない。
図で青で表わした線は、それぞれヨリ合わせるか三つ編みにする。同じ色の配線材で三つ編みにするとワケがわからなくなる。で、配線材は少なくとも3色は必要。黒(アースに使う)を含めて5色くらい用意すれば安全だ。お薦めパターンは、赤(電源系統に使う),黄色(入力信号系),緑(出力信号系),ブルーと黒で、どうにか間に合う。
ピンクで表わした線はシールド線。配線用だからなるべく細いものを選ぼう。これは1色で間に合う。基板側では芯線とシールド網線は別々の穴につながる。配線先、★印の箇所ではシールド網線はカットし、芯線だけ接続する。このときシールド網線が不用意に接触しないよう、熱収縮チューブを被せて絶縁しておきたい。
3pトグルSWからVRへの渡り線が1本あるのを忘れずに。底板に付ける電池ボックスを使わない人は、電池スナップの線は図の通り。電池ボックスの場合はスナップの線の代わりに7cm程度の線を基板と出力ジャックから出しておき、最後にボックス付属のスナップの線とつなぐ。つなぐ際にはきちんとハンダ付けをして、全体に熱収縮チューブを被せて絶縁する。
以上で配線は終わり。どこも間違っていなければソク完動するはず。
なお本機回路のアースは、入力ジャックのアース端子の一点でケースに落としている。これでケースがアースになる。入力ジャックのアース端子への配線を忘れると全体が「アース浮き」状態になり、ハムノイズの嵐に見舞われる。ケースがアースになるからこそ、出力ジャックにプラグが差さるとパワー・オンするわけだ。
■チェックと音出し■
配線が終わってからチェックしても後の祭りというものだが、やらないよりやった方がいい。全体を調べ直して図面と合っていることを確認しよう。
電池をつなぎ、出力ジャックに何でもいいからプラグを差して1分ほど様子を見る。ヘンな臭いや煙、火花は出ていないかな? 電池にも触れてみて、発熱していないのを確かめる。ミニ四駆みたいに電池が熱くなっていたら異常だ。
INにギターなどの楽器をつなぎ、OUTからアンプにつなぐ。このとき、ツマミはDRIVEがフル、DISTは最小、VOLも最小、TONEはどっちでもいい。アンプのヴォリュームを少し上げて、フットスイッチを踏み換え、原音が出ることを確認。次にVOLを徐々に上げてみよう。昔なつかしファズの音が聞こえてくるだろう。TONEで音色が変わる。DRIVEを少し絞るとディストーションっぽいサウンドに変わる。
さて問題のDIST。これを上げて行くと音量は小さくなる。その分VOLを上げてやる。サウンドはどう変わるか。DRIVEでの変化とはまた別で、ファズ音自体が変化するだろう。TONEを切り替えると、また違った味の音になる。DISTをフルにすると音量はかなり小さくなるが、VOLを上げれば対応できるはず。このときの音はとってもヘン。どこかブッ壊れたような、アタックだけファズがかかったような、何とも言えない音になる。DISTをフルテンにするのは、まあ趣味の問題としても、普通は適度に調整し、微妙な音色変化を楽しんでほしい。
第1回目でもあることだし、書きたい放題書けることでもあるしで、ヤになるほど長い説明になってしまった。いろんな理屈や、初心者向けのノウハウも書いたせいもある。
私の希望・理想としては、ハンダごてを握ったことのない人にも、この記事を機会に製作に参加してほしい。でも実際にはハンダづけの基礎から書くわけにもいかないから、初心者諸君には失敗覚悟で清水の舞台から飛び降りてもらいたい。
失敗といえば、このマシンは100%の再現性を保証する。つまり、どこも間違えずに作れば必ず所定の性能で動く。私自身、自分の作ったデータで、マシンをもう1台作って確認している。だから、不幸にして動かないとしたら、どこか間違っている。パーツ不良はまずあり得ない。
キツいことを書くようだが、もしも動かなくても私の責任ではない。困るのは「何度見直しても間違っていないのに動かない。どこがヘンなんでしょう」式の質問をもらうこと。トラブルはご自身で解決していただきたい。もっとスゴいのは、いきなりマシンを送ってきて「直して下さい」という人。たしかに直せないことはない。しかし他人の作ったマシンのトラブルシュートは、ほとんどの場合、最初から作るよりも手間がかかる。現状の忙しさからして、申し訳ないけれど、不完動の質問や修理は一切お断りするしかない。どうかご了承願いたい。
さて次回は何を作ろうか? 今のところ、アナログシンセまがいの音源のようなものを考えているけれど、予定は未定、お楽しみに。
■主要パーツリスト■
★基板上
1/4W型カーボン抵抗
200Ω*1,1k*4,1.2k*2,1.8k*2,3.3k*2,10k*6,15k*1,22k*4,
47k*4,100k*11,220k*1,1M*6
コンデンサ
セラミック 0.01*1
マイラorセラミック 0.001*1,0.002(0.0022)*1,0.047*2,0.1*3
電解 1μ*6,2.2μ*5,10μ*5(内1個は耐圧25V以上)
半導体
2SC945etc.*6,2SK30Aetc.*4,1S1588etc.*7,78L09(or08)*1
★基板外
ケース タカチTS-11*1
VR 1kB*1,100kB*2
スイッチ トグル3p*1,フットスイッチ ミヤマDS-136*1
ジャック モノラルSW付*1、ステレオSW無し(SW付でも可)*1
DCプラグ&ジャック……本文参照
OO6Pスナップ*1または電池ボックス タカチGL-006P*1
ツマミ 15φ程度*3
3ミリビス用スペーサ 3〜5ミリ*2,ビス・ナット*2組
この記事についてのご感想、ご希望、バグ指摘、もっと良い(ヘンな)定数のレポート、その他いろいろはaslのHandmade Projectまでよろしく。長文の場合は、お手数でも「珍品堂アナログ店」の住所まで、郵政省メイルでお願いします。
この記事の文章、図版、写真、プリントパターンの著作権は筆者・大塚明に帰属します。読者がご自分のためにコピー、製作することは無制限に自由ですが、個人・法人を問わず、この著作物をどんな形態であれ営利目的に使用することは固くお断りします。また記事内容の転載をご希望の場合は文書による契約を要します。……こんなこたぁ書きたくないけど、世の中、コスいのがいるからねえ。書かなくてもいい世界になることを念じてます。
